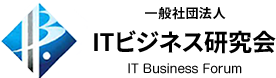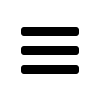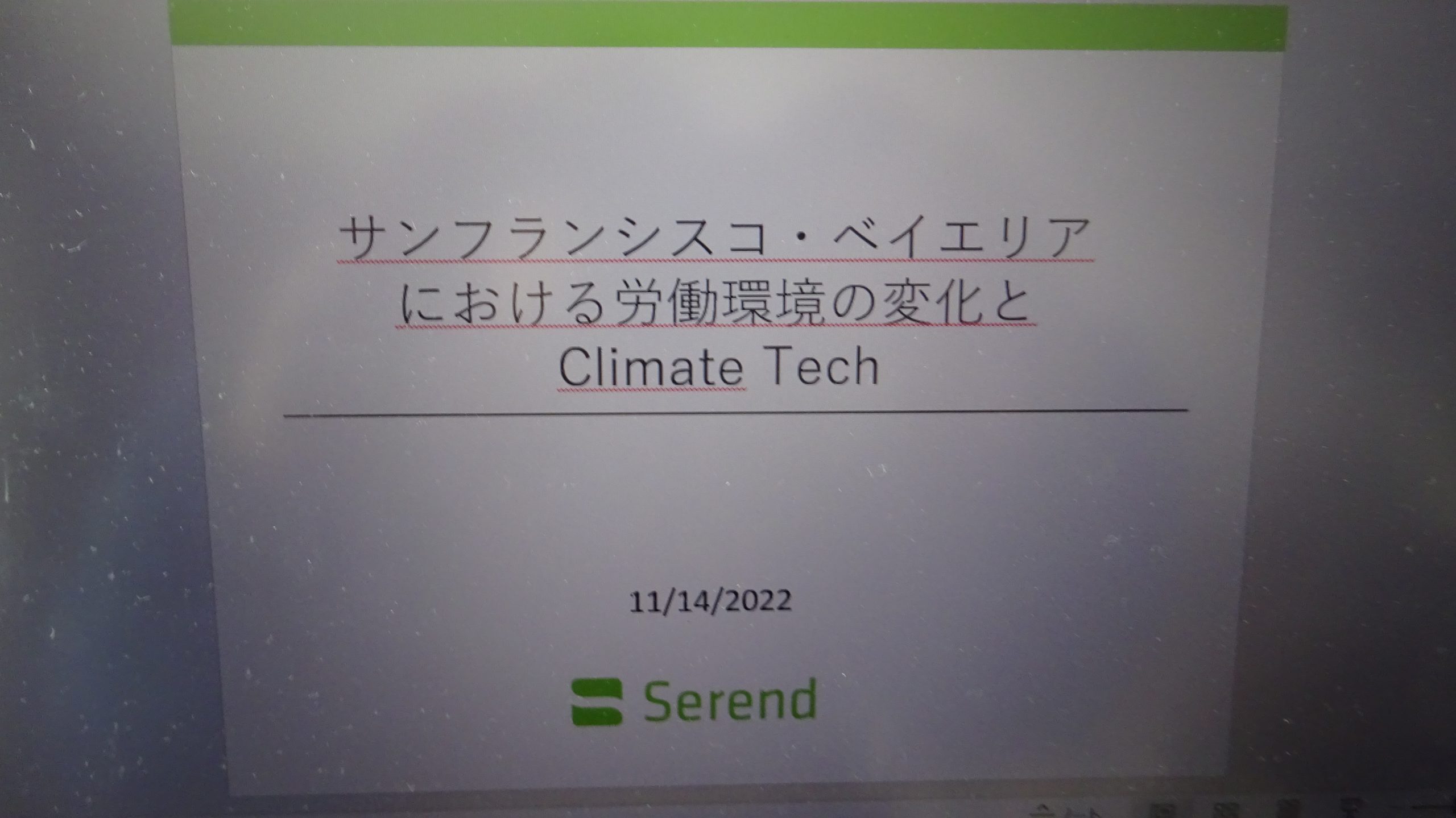「2021年の大量離職(The Great Resignation)から、2022年は静かな退職(Quiet Quitting)に変わってきた」。米シリコンバレー在住のSerend代表の大木美代子氏は11月15日、ITビジネス研究会の特別セミナーで、コロナ禍における在宅勤務が米国の働き方に変革を迫っている状況をこう表現する。
2020年のロックダウンで在宅を強制されたシリコンバレーで働く多くの人たちが「この仕事でいいのか」と、2021年に新しいことにチャレジしたり、キャリアチェンジしたりするために退職する。1年後の2022年には、今の仕事は続けるものの、働き時間はミニマムにする。ワークライフバランスともいえる。とくにメタやアマゾン、ツイッターなどの大量レイオフが新規採用を抑制したこともあって、辞めることはせず、仕事へのスタンスを変えているという。
ITエンジニアらの在宅勤務は、オフィスの役割を変えた。仕事からサロンの場へとなる。半面、オラクルなどの巨大オフィスは十分に活用されなくなっている。そこで、不満な経営者は従業員にオフィスに戻れと指示する。RTO(リターン・ツー・オフィス)と呼ぶそうだ。対して、従業員は在宅勤務を維持しようとする。これをWFH(ワーク・フロム・ホーム)と呼ぶ。従業員は週3日以上の在宅勤務を求めるのに対して、経営者は2日程度にしろなり、両者に軋轢が生まれている。
在宅勤務はベイエリアのエコシステムに大きな影響も及ぼす。とくにサンフランシスコの街にオフィスワーカーがいなくなり、バスなどの公共機関の利用者が激減する。レストランなど飲食店の営業が困難になる。サービス業の人たちにとって住みづらい街になっていく。その一方、ホームレスが増加し、犯罪も増える。中間層から富裕層はサンフランシスコにいる理由がなくなり、テキサスなどに引っ越す。ところが、そこにはハリケーンなど人の健康や生命、財産を脅かすことが次々に起こり始める。サンフランシスコ市長は、テック業に代わる新興産業を興す必要性を説いているそうだ。
そうした課題を解決するテック企業に注目が集める。Climate Tech(気象テック)だ。CO2排出量の削減や地球温暖化対策をテクノロジーで解決しようとするスタートアップで、モビリティやエネルギー、さらに金融サービスなどの関連事業への融資が21年上期に急増した。3000社以上あると言われているClimate Techの21年のディールは1611件(前年は1316件)、投資は56ビリオン(同31ビリオン)になる。在宅勤務は、産業の構造まで見直しを迫ることになる。なお、詳細な情報が必要な方は、事務局まで連絡をください。(田中克己)