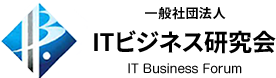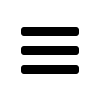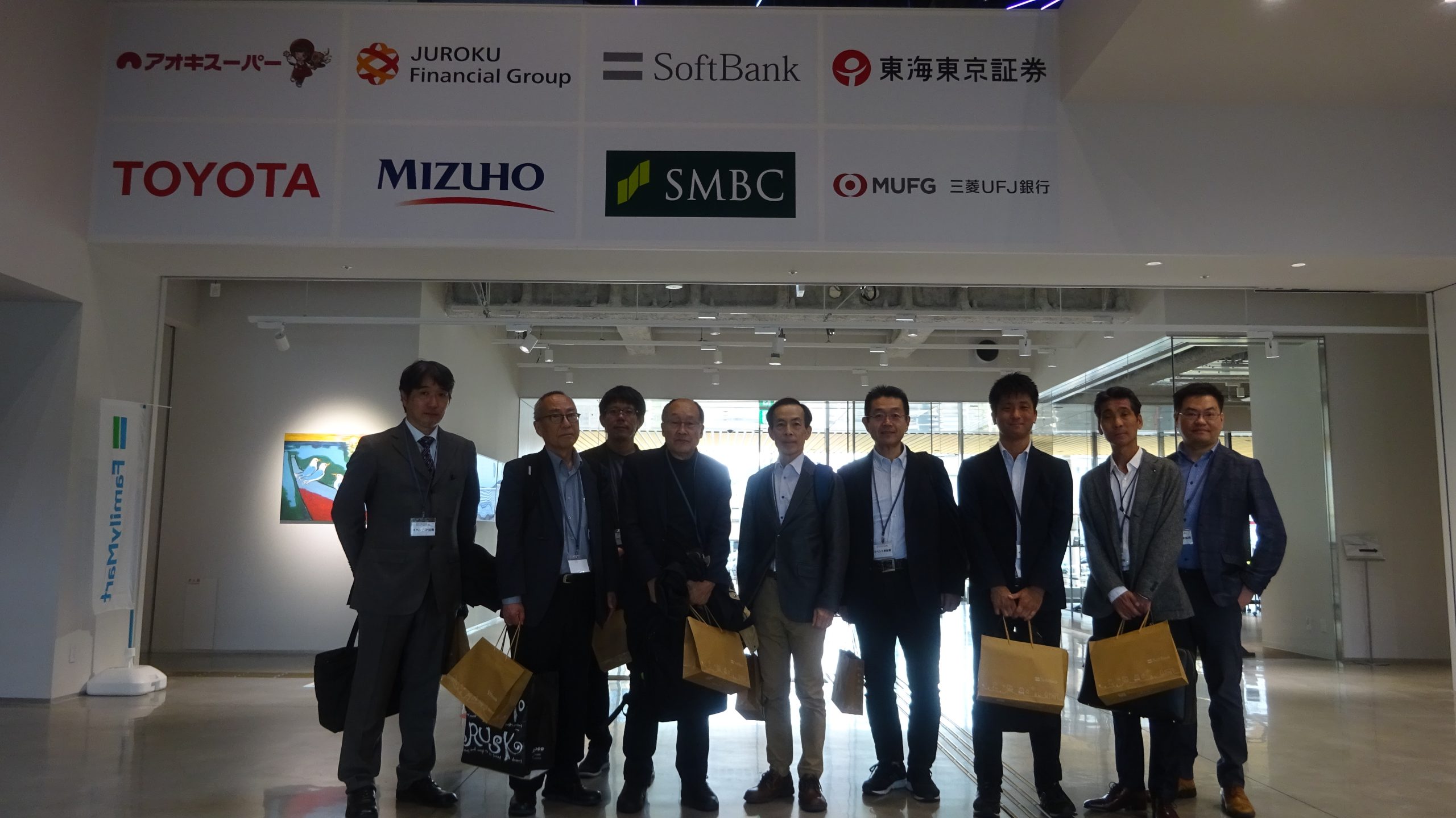一般社団法人ITビジネス研究会は4月16日、17日の2日間、名古屋市のスタートアップや支援施設などを視察した。今回で4回目になる国内スタートアップの視察の参加者は10人だった。
初日の16日は、2024年10月にオープンしたインキュベーション施設STATION Aiを訪問した。DXやSaaS、AIなど約500社のスタートアップと事業会社らがスタートアップの育成や協業のエコシステムを形成し、新規ビジネスの創出に取り組んでいる。施設は7階建ての2万3000平方メートルのスペースにコワーキング席、固定席、個室席のほか、イベントスペース、カンファレンススペース、さらに託児所、ホテル、スポーツジムを備える。とくに大企業の課題解決と新規事業立ち上げをスタートアップの技術や知識を借りるオープンイノベーションに力を入れており、最初の3カ月間に約200回のイベントを開いた。その8割は入居者によるもの。スタートアップへの主な支援は資金調達や人材採用などになる。事業会社に対しては、オープンイノベーションの実現に向けてのゴール設計、協業先の探索、そして事業を生み出し、大きく育てるというフェーズごとの支援を用意する。社会人向け起業家育成や学生向け起業家育成のプログラムもある。前者は岐阜県の十六銀行、後者はみずほファイナンシャルがそれぞれ取り組んでいる。

データ活用コンサルのNousLagusとAI人材研修のKANNONのピッチ
スタートアップ2社のピッチもあった。1社はNousLagus(ノスラゴス)だ。ソフトバンクのデータエンジニアだった守屋恵美代表取締役CEOが5年前に立ち上げた。スマートシティなど地域創生の課題解決にデータを活用することに取り組んでいた守屋氏は、そのノウハウを活かし、「キクメモ」と呼ぶ、社内ヒアリングからベンダーとの連携に必要な提案依頼書作成までを支援したり、社内外の情報連携を安価に実現させたりするためのコンサルティングを開発する。守屋氏によると、例えばAさんが休むと仕事が進めなくなる。こうした属人化を解決するために、企業はデジタル化を考えるものの、何をどうしたらいいのか分からない。どんなツールを入れたらいいのかも分からない。実は1社あたり平均11本のソフトを活用しており、それらの管理は容易なことではない。11本のソフトの連携もできていないことが多い。例えば、物流会社と荷主のデータが連携できれば、コストを大幅に削減できる。「それには、このソフトを使って、こうしたらどうだろう」と提案する。そんなコンサルティングを中堅・中小企業向に月額5万円から提供する。大手に依頼したら5000万円くらいになる支援内容だという。
もう1社は、アクセシビリティ向上サービス「フェアナビ」を運営するKANNONだ。名古屋大学発スタートアップで、誰もがAIを活用できるための研修を開発した。イギリスで暮らす山下青夏代表取締役によれば、2日間の集中プログラムを受講すれば、自発的に課題解決にAIを活用する人材になれると自信をみせる。受講費用は1人あたり約40万円だが、助成金を活用すれば実質10万円で済むという。製造業や土木、金融、サービスなど約30社の企業が研修を受け、受講者の満足度は9.4とかなり高かったという。成功事例には、製造業の経営データ分析が240分から30分に、社商品の宣伝のためのニュース原稿作成が120分から20分に、それぞれ削減したなどがある。

ソフトバンクの先端ソリューション体験施設
STATION Aiを運営するソフトバンクは、企業の事業成長やDXを支援する先端ソリューションを体験できる施設を設けている。EBCと呼ぶもので、5GやAIなどの先端技術を駆使し、例えば、世の中の不満をプラスにするソリューションを開発する。不満買取センターが1回あたり1円で集めた約4000万件の消費者の不満や課題の情報を活用する。開発中の空飛ぶ基地局の模型も展示する。スターリンクは地上500Kmに対して、幅約70メートルの空飛ぶ基地局は地上20Kmを飛び回り、地域インフラ不足やドローン活用など、いつでもどこでも通信を可能にする。コールセンターへの消費者の声を変換するソフトも東大と共同開発する。怒った声を優しい声に変換するもので、ソフトバンクのコールセンターでPoCをしているところ。

名古屋市が取り組むスタートアップ育成支援
4月17日の午前は、名古屋市の経済局スタートアップ支援課を訪問した。5~6年前に新設した同課は、Jスタートアップ・セントラル・ジャパン・スタートアップ・エコシステム・コンソーシアムなどを支える。名古屋のグローバル企業との協業を推進する同コンソーシアムは起業家人材の輩出、オープンイノベーション、海外ネットワークの拡大、ファイナスの4つに力を入れる。名古屋大学や名古屋工業大学を中心に起業家育成支援のプラットフォームという位置づけにもなる。現在、44社のスタートアップが登録し、事業会社とのマッチングなどを支援する。名古屋市も、中部経済連などと協力し、人材育成などを推進する。その1つが、小中高生への起業家やキャリアの教育になる。モデル校を設定し、小学生には経済の仕組みなど専門家による授業をする。IT活用プログラム、DEEPTECHプログラムもある、宇宙をテーマにするワークショップを開催し、優秀な学生は海外研修をさせる。
名古屋コネクトと呼ぶ月2回、起業家や投資家、CVCCなどが集まるオープンイノベーション会合も開く。事業会社からの相談があれば、最適なスタートアップとのマッチングもする。行政の課題解決をPoCしたり、スタートアップからの社会課題解決の提案をPoCしたりもする。例えば、商店街や街づくりの課題解決をスタートアップが提案すれば、補助金を出す。海外向けマインド作りやピッチの仕方を指導もする。シリコンバレーの起業家やVC(ベンチャーキャプタル)に依頼する。JETROのシンガポールなどで研修もさせる、25年2月には、中部経済連などとスタートアップのエコシステム形成を目指すイベント、TECHGALAを開催し、約5000人が起業家や事業会社らが参加した。(写真はスタートアップ課の課長補佐、佐橋学氏、主事の荒井健太氏)

ヒューマノイドロボ開発のAMATAMA
午後は再びSTATION Aiを訪ね、AMATAMAの堀内雄一代表取締役にヒューマノイドロボットの動向に聞く。堀内氏は22年に国連が公表した2050年に5億人の労働人口が不足するとの調査に注目した。人の代わりに働くロボットのニーズが高まると考え、ヒューマノイドの開発に取り組み始めた。そこには機械だけではなく、医学など様々な知識、技術が必要になる。ニューラルサイエンスやバイオメカ、さたに階層型コンピューティングの研究開発をする。
堀内氏によれば、ホンダが開発した二足歩行ロボットASIMOなどの次の世代のロボットは、人の骨格を形成し立ち上がりも可能になる。ただし、人には約1000億個のセンサーがあり、これからの情報をLLMで学習させるのは不可能に近い。メタやオープンロボットはそれに取り組んでおり、大量のサーバーと大量の消費電力が必要になる、現実的ではない。対してヒューマノイドは低消費電力を実現する。本格化するのはAGI(汎用人工知能)が登場する2028年になる。それぞれの職能の学習プログラムを学び、まずは軽作業の仕事から任せる。例えば、警備会社がグリーンランドの警備を請け負ったら、ヒューマノイドに警備アプリをインストールするといった具合だ。建設現場で働く、レストランで働く、などそれぞれの職能、職場にあったアプリを開発するということ。なので、時間帯でアプリを変えれば、異なる仕事をこなせる。同社はそのアプリを稼働させるプラットフォームを提供するビジネスに特化する。
ロボットを開発、製造するのは、自動車メーカーなどを想定する。5億台のロボットを生産するには、年に数百万台を製造できる工場が必要になる。なので、自動車メーカーが最有力候補というわけだ。AMATAMAはそのためにデザインガイドラインを作成し、製造会社などに提供する。堀内氏によると、スマホにおけるアンドロイドのビジネスに近いという。スマホは各メーカーが作り、グーグルのOSを利用する。そんな関係にする。(田中克己)
以上、訪問した企業、会員の皆様に紹介することも可能。事務局に連絡をください。